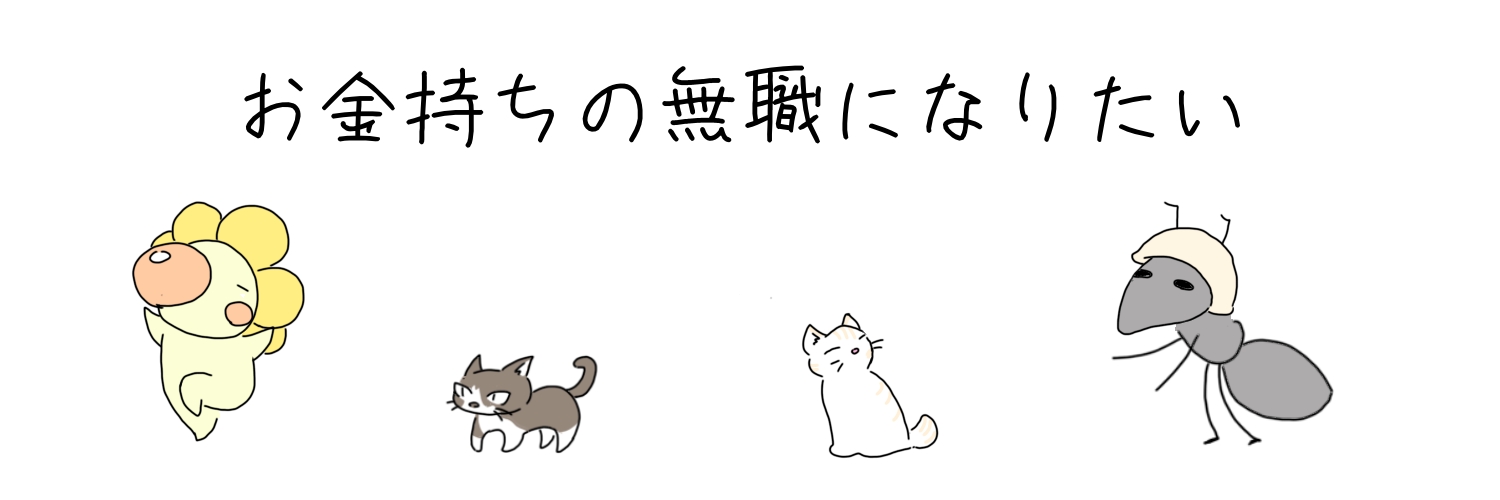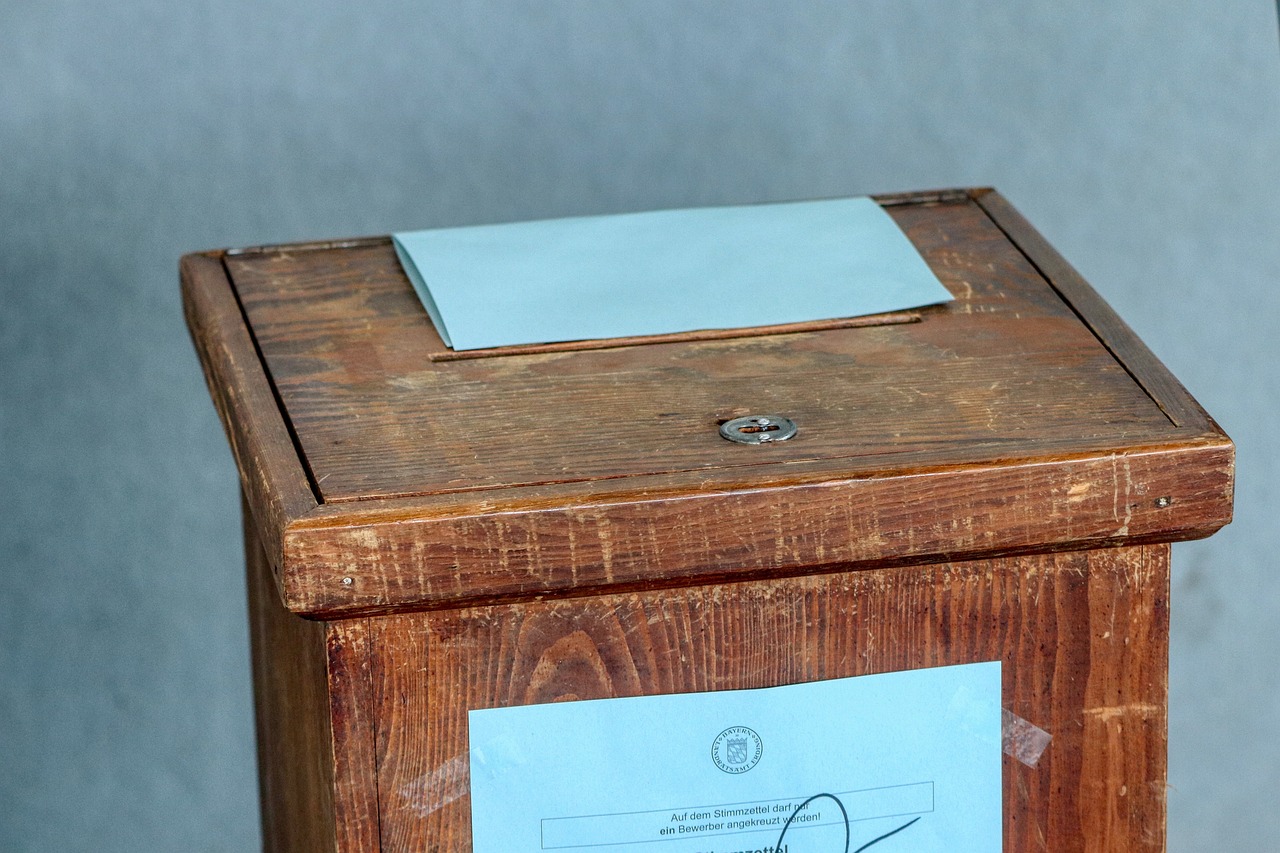金融所得課税、社会保険料に反映する方針が閣議決定される
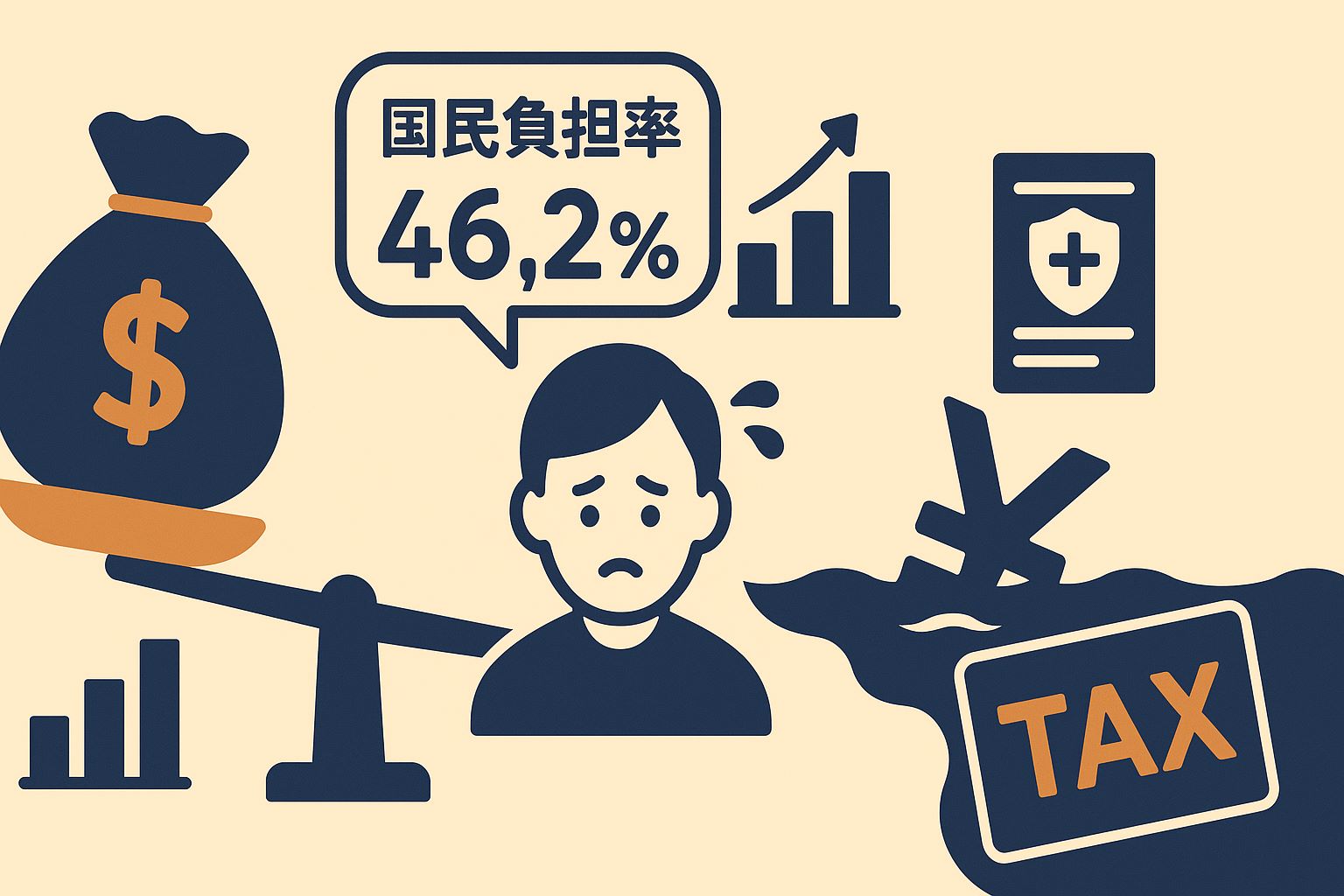
おおよそ1か月前程でしょうか。タイトルにもある「金融所得課税が社会保険料に反映されてしまう」といったものがニュースにも取り上げられていました。今回はこのテーマを公式ソースを元にお話したいと思います。現政府がどのような方針で金融所得に対して課税強化を進めているのかを認識してもらえればと思います。
閣議決定による金融所得課税の方針
1. 改革工程(全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋)
2023年12月に政府が閣議決定した「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程表2023)」において、次の方針が明記されています:
「国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方について、税制における確定申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつつ、検討を行う」
ここで、金融所得(株式の譲渡益・配当等)を申告の有無にかかわらず保険料に反映させることの「検討」を2028年度までに進めるとしています。
2. 骨太方針2025(令和7年6月13日閣議決定)
2025年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針2025)」では、医療・介護保険における金融所得の反映に関する制度設計を進める旨が明記されています:
医療・介護保険における金融所得の勘案は、昨年末に閣議決定された改革工程において、「能力に応じた全世代の支え合い」の観点から、2028年度までに実施について検討する項目に位置づけられています
そして同時に、政府は金融所得(株式の売却益や配当など)を医療・介護保険料に反映させる制度設計を進める方向であることが報じられており、注釈に以下の内容が明記されています:
医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、具体的な制度設計を進める。
まとめ
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| 改革工程(2023年12月閣議決定) | 申告の有無に関わらず、金融所得を国保・後期高齢者医療・介護保険料に反映させる検討を2028年度までに進める |
| 骨太方針2025(2025年6月13日閣議決定) | 医療・介護保険料への金融所得の反映を含む制度設計を進める旨を明記 |
政府としては、この方向性を2028年度までに結論を出す予定です。
引用元:「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程表2023)」、 「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針2025)」
この一連の流れで重要な観点として、確定申告の有無による不均衡を是正することがこの制度設計の前提条件となっています。現行制度で「申告の有無」によって見え方が変わる金融所得(株式譲渡益・配当等)を、申告あり/なしにかかわらず、医療保険・介護保険制度の保険料算定の対象に組み込む方向で検討するという方針を示しています。
実際の負担額シュミレーション
2028年までに最終的な方向性が示されそうですが、実際に制度が決定したらどのくらい保険料負担が増えるのか?これをシュミレーションしてみたいと思います。シュミレーションはChatGPT(通称:チャッピー)にお願いしました。
※前提条件
- 試算対象:国民健康保険 + 後期高齢者医療 + 介護保険(いずれか)
- 居住自治体:東京都23区(標準的な料率を採用)
- 年齢:
- ケース①:65歳以上(高齢層)・介護保険対象
- ケース②:40歳未満(現役層)・介護保険対象外
- 所得水準:年金等と別に、金融所得を100万~500万円と仮定
- 所得区分:所得割+均等割ベース(住民税ベース)
- 税金:20.315%の源泉徴収(今回の試算には加味しない)
ケース別試算(65歳以上・高齢世帯)
| 金融所得(例:配当や譲渡益) | 年間保険料増加額(概算) |
|---|---|
| 100万円 | 約4〜6万円(国保+介護) |
| 200万円 | 約8〜12万円 |
| 300万円 | 約12〜18万円 |
| 500万円 | 約20〜30万円 |
※配当や譲渡益は住民税所得に加算されるため、それに比例して所得割部分が増加します
※高額所得者には保険料の上限(年間約100万円前後)もあるため、それ以上の上昇は一定で頭打ちになります
ケース別試算(40代・現役世帯)
| 金融所得 | 年間保険料増加額(概算) |
|---|---|
| 100万円 | 約3〜5万円(国保のみ) |
| 200万円 | 約6〜10万円 |
| 300万円 | 約9〜15万円 |
※介護保険料が含まれないため、高齢者よりは若干負担が軽くなる傾向です
補足:試算モデル式(参考)
年間保険料増加額 ≒ 所得割率 × 金融所得額
所得割率例(東京都23区の場合)
- 国保:7.0%前後
- 介護保険:1.8%前後
- 後期高齢医療:9.5%前後(自治体により異なる)
ポイントまとめ
- 所得が200〜300万円規模ある高齢富裕層の場合、年間の保険料負担は10万円以上増加する可能性が高い
- 負担は自治体や世帯構成により変動(最大限度額や均等割の影響を受ける)
試算をしてみましたが、結構な負担増加になるなぁとの印象です。国保のみでも7%前後も差し引かれるのは相当しんどいです。源泉徴収で差し引かれる分も含めると、約30%も利益が吹き飛ぶこととなります。リスクを負って投資をしている投資家心理を冷やしてしまっては、国が謳っている「貯蓄から投資へ」の動きに水を差す形になってしまうのではないのでしょうか。
おわりに
今回は金融所得に対する政府の課税方針についてお話してみました。現政権が金融所得課税に対して今までどのような方針・考え方をしていたのか、今一度振り返るのに参考としていただければ幸いです。
話は少し変わり、明日はついに参議院選挙の投票当日です。ここ最近は政治関連の話題ばかりでしたが、明日で一旦一区切りとなります。前にもお話しましたが、今回の選挙は日本の未来の重要な分岐点になると思っています。どの政党が票を獲得するかで未来は大きく変わります。仮に現与党が過半数を取ってしまったら、自民党は裏金やらなんやらまたやりたい放題、国民に負担を強いていくと思います。投票しない方には今の政治に文句を言う資格はないので、是非投票所に行って自分の意思表示をしてもらえればと思う今日この頃です。